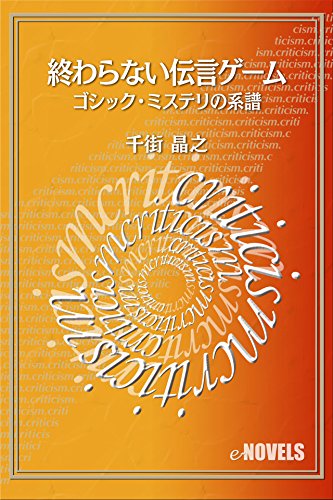【本ブログ記事では北山猛邦『月灯館殺人事件』の内容への言及があります。ご注意ください。】
わたしたちがおこなっていたのは、ほんとうに「伝言ゲーム」だったのでしょうか。
北山猛邦『月灯館殺人事件』を読み終え、いっときそのような感慨を覚え、いまこのブログを書いています。といっても多くの方は「伝言ゲーム」という言葉にすぐに思い当たるものが浮かばないかもしれません。
自分のいう「伝言ゲーム」とは、千街晶之によって書かれ、『創元推理10〈'95年秋号〉』に掲載された評論「終わらない伝言ゲーム ゴシック・ミステリの系譜」および、そこで語られているミステリの系譜そのものを指しています。
本格ミステリに散見される、ゴシック・ミステリ(≒館ミステリ)という存在がなにものであるのかについて、95年の時点で振り返り、しかしその射程は未来の、いま現在も書かれ読まれているであろうミステリをも捉えているすぐれた文章で、いまでもその視点は色あせていません(現在はkindleほかの電子書籍で読むことができます)。
といっても、話を急ぎすぎたかもしれません。
改めて『月灯館』の話をしましょう。以下簡単なあらすじを記します。
デビュー作を上梓してから二年半、次作が書けず悩んでいたミステリ作家の弧木雨論(こぎうろん)は、ミステリ作家版「トキワ荘」とでもいうべき「月灯館」を訪れる。そこは『本格ミステリの神』と呼ばれた男、天神人(てんじんひとし)が買い取った建物で、多くのミステリ作家たちが執筆のために過ごしてきた場所だった。しかし12月21日の冬至の日、食堂に集められた「月灯館」の住人たちは、カセットテープから流れる謎の告発を受けることになる。
『この館に集いし七名の作家は、【本格ミステリにおける七つの大罪】を犯した堕天使としての父と子と読者(せいれい)の名のもとに処刑されることが決まりました』
はじめはなにかの冗談と思っていた作家たちだったが、翌日、天神人の首なし屍体が密室で発見されたことで事態は変わる。それを期に【七つの大罪】に見立てられた連続殺人の火蓋が切り落とされるーー。
外部から閉ざされた雪の館。密室。首切り死体。見立て殺人。「城シリーズ」を上梓してきた北山らしい、まさしくごてごてとした「館ミステリ」そのもののプロットで物語は進んでいきます。しかし旧来の「城」における北山とは少々違っている部分もまたあります。なにかというと、本作においては、本格ミステリへの自己韜晦、苛立ち、そして開き直りが終始、ちりばめられているという点です。
さて。では本作のこうした記述を作者自身による読者への告白、あるいは告発として読むことができるでしょうか。これについてざっくりと考えていきたいと思います。では、そもそも作中で宣言される七つの大罪とはなんなのでしょうか。
以下、列挙してみましょう。
一、傲慢 二、怠惰 三、無知 四、濫造 五、盗作 六、強欲 七、嫉妬
と、なります。そこでたとえば作中人物のひとり、日向寺はミステリマニアが嫌いだといい、それに対して反論を受けると次のように露悪的に宣言しています。
「でもあなたが書いているのは、そういう方たちに向けた小説ではありませんの?」
金友が云う。
「その通り! そういう奴らに向けて『どうせお前らこういうのが好きなんだろ』ってエサを投げてんのさ。ポイ、ポイ、ポイってな。ぎゃははっ」
このように本作では終始、上記のようないささかリスペクトを欠いた言葉が散見されます(それは、ミステリに対する罪といってもいいかもしれません)。
正直、先に記した七つの大罪がすべて納得のいくものとは即座には思えませんが(いち読者の意見です)、しかしとりわけ、ここにおける三者ーー無知、濫造、盗作、といった話題はミステリの歴史、あるいは新本格30年の歴史とは切っても切り離せないように思えています。
つづけましょう。
以下に、物語後半に挿入される、弧木の印象的なモノローグを引用します。ここには現代ミステリ作家らしい悩みが赤裸々に吐露されています。
弧木がその世界を知った時にはもう、進化は究極を迎えていた。百七十年以上にわたって自然淘汰を繰り返し、生き残った優秀な作品だけが、弧木の本棚に収まっていた。(…)
そもそもーー弧木の考えでは、現代の本格ミステリは、あくまでアポトーシス的な役割しか持ち得ない。百年前にすでに完成された様式、すでに完成された作品を、美しいまま次の百年に導くために、あらかじめ死ぬことを約束された細胞の一つ一つでしかないのだ。(…)
結局のところーーそれっぽければそれでいい。(…)
そう、だから問題は「それっぽさ」なのではないでしょうか。
本作のなかでは、いくつか皮肉にきこえる話題に触れる瞬間があります。たとえば、作家がアガサ・クリスティやホームズなどの古典にあたることを怠っていること。たとえば、ミステリといっても、ここ二、三十年に一般化した「雰囲気」だけを借りて、そのジャンルの純度を下げる作品を世に出していること。たとえば、先人のトリックをそのままパクってしまっていること。
しかし、驚くべきことに、わたしたち「読者」は、そのような「傲慢」で「濫造」されるようなミステリにでさえ、楽しみを見出すことができてしまいます。
なぜならわたしたちも同様に「無知」であるから。わたしたち読者はよほどのことがなければ、百七十年あまりの歴史には触れようとはしないのです。だからこそ、『月灯館』では、過去のミステリから盗用された(というていの)トリックによって殺人事件が構成されてます。そして館に集ったミステリ作家たちは、その作品を知らないがゆえにすぐさま謎を解くことができません。これは皮肉といっていいでしょう。
ですがそれだけではありません。第一の殺人事件。これは古典的な、というよりかなり既視感のあるトリックだと明かされるのですが、そこにひとつ最新のガジェットが追加され、アレンジされています。
自分の記憶によれば、かつてミステリ読者・作者・評論家はそれを、ミステリの延命策として肯定的に捉えていたように思います。たとえトリックの鉱脈が尽きたとしても、新しい時代の技術が、ガジェットがまたトリックを生まれ返らせてくれる。だからミステリは大丈夫なのだ、と。
(おそらく)そうした前提があるうえで、本作においてそれは、ただのチープなコピーアンドペーストとして認識されています。そこに独創性などはない、と開き直るように書かれています。著作権保護期間の終了*1を待つまでもなく、ミステリのトリックは、歴史は簡単に忘れ去られ、そしてまたおなじようなミステリが現れ消えていく、という退廃的なジャンルでしかない。だから小説は問いかけています。
その虚しさを受け入れる覚悟はあるか?
本作のあの、どこまでもとって付けたかのような、てきとうにもほどがあるフィニッシングストローグはまさしくそのようなコピーアンドペーストによる「それっぽさ」が実践可能である、という宣言にほかなりません。
だとするなら、『月灯館殺人事件』は本格ミステリというジャンルのゆるやかな進化の終わりを告発する作品なのでしょうか。むろん、そういった部分もいくぶんかあるでしょうが、今回はそれとは違う部分も考えてみたいと思います。
改めて「終わらない伝言ゲーム」の話をしましょう。
千街晶之によるこの評論では、日本ミステリにおける進化の歴史を「伝言ゲーム」というものとして表現しています。おなじメッセージを伝えようとしているのに、いつの間にか言葉が変わっている、というあの遊びです。千街は、95年の段階の、新本格派への「館ミステリ」の流れを以下のように、系譜として並べています。
英国の、ゴシック・ロマンス作家たち → 米国黄金時代の本格ミステリ作家たち(ヴァン・ダイン、クイーン、カーら)→ 戦前日本の探偵作家たち(江戸川乱歩、小栗虫太郎ら) →『幻影城』派及び島田荘司、笠井潔ら → 新本格派及びその周縁の作家たち
千街は、島田荘司や泡坂妻夫が『斜め屋敷の犯罪』や『乱れからくり』で海外作家を参考にするというより、国内作家を模倣しつつ書いていることを指摘しています(もちろん細かい部分では違うことも述べていますが)。
ですから、これが「伝言ゲーム」のかたちというわけです。
戦前・戦後の探偵作家たちが米国の本格ミステリ(空間的な異文化)を自分なりに咀嚼したように、今度は彼ら過去の探偵作家たちの業績(時間的な異文化)が新世代の作家たちによって咀嚼される番が廻ってきたのである。
また、これらの「伝言ゲーム」は新本格の勃興により、たしかなものとして証明されました。そして幾度となく、その「伝言ゲーム」という言葉じたいもまた神格化されていきます。なぜならそれはわたしたちにとって当たり前のものだから。であれば北山猛邦の「城シリーズ」はやはりこの「伝言ゲーム」の末尾に加えるべき系譜といっていいでしょう。
しかし『月灯館』を読んだわたしたちはもう知っています。
あの遊び心に満ちた「伝言ゲーム」はいつしか、ただのコピーアンドペーストになりさがってしまった。営為はただの虚しさにとって変わり、わたしたちはそれを無自覚に享受している。
なぜでしょうか。
ここには「器」があったからです。本格ミステリとしての「コード」といってもいいでしょう。それさえ守っていれば、「それっぽさ」は担保されてしまう。音楽のコード進行そのものに著作権がないように、それっぽさは簡単に解析され、コピーされてしまう。だからわざわざミステリのなかであたらしさを独創する必要すらない。加えていうのであれば、古典を読まなくともこのコードは手軽に再現できてしまう。前述したように、『月灯館』のラスト一行はコピーアンドペーストです。
さて、ここで大きく誤読してみましょう。
おそらくこうしたコード文化にライドした作品たちの濫造こそ、本作で描かれてきた「(新)本格ミステリの罪」だったのではないでしょうか。
なぜならとある人物が新本格ムーヴメントを後押ししてくれたことによって、わたしたちはこのような罪を受けているのですから。そしてまた、そのような「それっぽさ」の期待を持たれ、応えていった作家として北山猛邦自身をあげることは決して突飛ではないでしょう。彼もその期待のなかで読者から作者になり、文化に耽溺し、ライドして、歴史に加担したひとりだったのではないでしょうか。
そしておそらく、わたしたちはその源流を、はじまりを言い当てることができるはずです。また、その歴史に擬せられた作家は物語で殺されました。わたしたちの読書を、ミステリを、そして罪を生みだしたがゆえに。その作家はかつてムーヴメントを牽引しましたが、しかし世界に物語があふれてしまい、ジャンル全体のクオリティコントロールができなくなりました。そのことは作中の手記にも書かれていることでしょう。
(…)そこに『本格ミステリの神』と呼ばれた男がいた。(…)
まるで神話だ。かつて神だったものが、堕落し、追放される物語。この事件も、千年語り継がれれば神話になり得るだろうか。いや、おそらく千年どころか、あと数日もすれば、この物語を語り継ぐ者は一人も生き残っていないかもしれないーーそして誰もいなくなった。弧木はそう考えずにはいられなかった。
神のいる世界は楽園だったかもしれません。しかしそれが過ぎ去ったのちは、ほんとうの人間の歴史がはじまるはずです。陳腐化したコピーアンドペーストを罪として認め、「伝言ゲーム」に「新本格」に神話を、浪漫を見出さず、ただただ生きていくための。そこからもう一度、一から歴史をはじめなくてはならないのではないか。
自分にはそう思えてなりません。
はい。そうです。
だから殺されたのは、『本格ミステリの神』そのものなのです。
すなわち、ゴッド・オブ・ミステリーにほかなりません。
それは、その名前はーー。
「島田荘司です」
*1:作中の事件が2016年であることに注意。