【※本記事ではTVアニメ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト 』および『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 』の内容言及をふくみます。未見の方はご注意ください。】
「私たちはもう 舞台の上」
ーー『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 』より。
1970年11月25日「三島事件 」
今年も過ぎてしまいましたが、11月25日は三島由紀夫 の命日でした。
1970年11月25日、作家である三島由紀夫 は午前11時ごろ、陸上自衛隊 市ヶ谷駐屯地に入り、彼の組織した「楯の会 」メンバー数名とともに総監・益田兼利陸将に面会し、彼を捕縛、総監室にバリケード をつくって立てこもり、総監を人質にするかたちで駐屯地の自衛官 を総監室のある本館前に集合させるよう要求します。
その後、彼はバルコニーに立ち、自衛官 たちに向かって演説をおこないました。
この経緯や演説内容を詳しく知らなくても「おまえら、聞け。静かにせい。静かにせい。話を聞け。男一匹が命をかけて諸君に訴えているんだぞ。」 といったフレーズや楯の会 の制服に身を包んだ三島由紀夫 が腕を振り上げ激を飛ばしている報道写真は、みなさんもどこかで触れた経験があるのではないでしょうか。
やがて演説を終え、総監室に戻ってきた三島は彼の主張(憲法改正 )が自衛官 たちに受け入れられなかったことを確認し、その場で割腹自殺をおこないます。
これが世に言う、「三島事件 」 のあらましです。
まだ『スタァライト 』 の話ではありませんが、もうすこしだけつづけさせてください。わたしが三島由紀夫 作品を読むようになったのは(といっても数は多くありませんが)、その右翼的な括弧付きの「美学」、国粋主義 や天皇 制に向かう側面ではなく、彼の作品に時折、顔を出してくるゲイネス に興味があったためです。
『仮面の告白 』異性愛 関係に幻滅することまでも。このあたりの描き方については、橋本治 『「三島由紀夫 」とはなにものだったのか』
wedge.ismedia.jp
また伊藤氏貴『同性愛文学の系譜 日本近現代文学 におけるLGBT 以前/以後』 では、『仮面の告白 』の主題を川端康成 作品と対比して、以下のように述べています。
さて一方『仮面の告白 』における主人公の「同性愛」に関する認識は全く異なる。それはれっきとした〈告白〉の対象であり、主人公は終始罪悪感につきまとわれている。つまりは同性愛を恥じているのであり、だからこそカミングアウトが主題化されるのだ。だから『仮面の告白 』は『同性愛文学の嚆矢』では全くないが、『同性愛者 文学の元祖』と言うことはできる。(太字は傍点)
念のため伝えておくと、わたし個人は伊藤の論にすべて同意はしません。なぜなら三島の存在をひときわ大きく強調すると、かえってそれ以前にも過去の作家たちが「同性愛」を言葉や定義上ではなくとも、その「苦悩」や「罪悪感」を一見そうとは「見えないかたち」で語ってきた(同性愛者の系譜、連続性の)歴史を捨象しかねない 可能性があるからです。
ただ、すくなくとも文学史 上における同性愛表象としての言及数が他の作家に比べて圧倒的に多く、詳細に研究され、それゆえに影響圏も広かったことを否定する理由はありません*1 。とはいえ、このあたりは本記事における本筋ではありません。
あくまで前説、あるいは三島由紀夫 に対するわたしの関心がどこにあるのか、という補助線のひとつ程度に思っていただけると助かります。
『劇場版 スタァライト 』と『Mishima: A Life In Four Chapters』について
VIDEO www.youtube.com
『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 』 はTVアニメシリーズ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト 』 の正統続編にあたる作品です。
正確には、そのあいだに『少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド』 というTVシリーズ を再編集した劇場総集編(一部新規映像追加)があるのですが、上映館としては『劇場版』よりも圧倒的にすくなく、作り手側としても、必ず見なくてはならない、といったアピールをした作品ではなかったように思います。もちろん『ロロロ』を見ることよって得られる部分はありますが、見なかったからといって『劇場版』で置いてけぼりになることは基本ないかと思います。
さて、その『劇場版』ですが、TVシリーズ からは作中時間がある程度経過しており、主人公ら99期生はすでに高校3年生、卒業先の進路を見据えながら残りすくない学生生活を過ごしている状態です。
冒頭の学内シーンでは、主人公・愛城華恋は後輩である1年生たち(101期生)を複数の指導教室の見学に連れていき、TVシリーズ に登場した主要メンバーたちを改めて観客にテンポよく紹介しつつ(ある程度はTV第1話前半の反復と差異にあたるでしょうか)、担任である櫻木先生との進路面談のシーンが並行してはさまれることで、それぞれの生徒が目指そうとしている進路が語られていきます。
しかしまた、TVシリーズ での〈オーディション〉を終えたあと、彼女たち99期生は演者としては停滞状態に陥っており、それを表立っては口にしない自己欺瞞 のなかにいることも徐々に明かされていきます。
やがてその不穏さが目を覚ますように、その停滞の先には舞台少女としての「死」がある 、と大場ななが〈皆殺しのレヴュー〉 とともに否応なしに突きつけ、物語は急速に動き出していきます。
「列車は必ず次の駅へ。では舞台は? 私たちは?
私たちもう……死んでるよ」
「あの日、私は見たの。〈再演〉の果てに、私たちの死を」
今回、わたしが考えていきたいのは、この大場ななという少女の思想がどのように劇中で変化していったのかについてです。加えて、この大場ななと星見純那の実質的なバトルシーンである〈狩りのレヴュー〉では、露骨に三島由紀夫 表象を取り込んだ うえでの表現が選択されていることを、本作の監督である古川知宏が2021年におこなわれたインタビューで明かしています。
tree-novel.com
純那とななの劇場版レヴューである〈狩りのレヴュー〉では三島由紀夫 と接続する演出があります。
ーーどの作品でしょうか。
三島由紀夫 を主題にした『Mishima: A Life In Four Chapters』という映画がありまして。製作総指揮はフランシス・フォード・コッポラ とジョージ・ルーカス ! 残念ながら日本未公開ではありますが、これがまぁ最高の映像の連続で。
この映画でも金閣寺 の描写があります。少年が金閣寺 の美しさに魅了されるんですが、そこで金閣寺 が真っ二つに割れちゃうんですよ! 「えっ金閣寺 が割れちゃうの!?」と。割れた内側が美しい黄金の「平面」なんですよ。そこに反射する光が主人公を圧倒する。
この演出を使いたい……とずっと思っていて、劇場版を作ってるとき小出君とが「『Mishima』やっちゃいますか?」と盛り上がった結果です。
ですからわたしは、この「大場ななと三島由紀夫 を接続する演出」 という点をきっかけにして、改めて『スタァライト 』を考えたいと思ったのです。
『Mishima: A Life In Four Chapters』について
VIDEO www.youtube.com
『Mishima: A Life In Four Chapters』 は、三島由紀夫 が1970年11月25日に自宅で起床し、楯の会 メンバーの運転する車で陸上自衛隊 市ヶ谷駐屯地に向かうまでのあいだ、自身の主要作品の再現映像を(彼の人生となかばオーバーラップさせるかのような半回想形式で)はさみつつ、やがて駐屯地総監室に立てこもり、バルコニーでの演説を終え、割腹するまでの出来事を描いた伝記フィクションともいえる映像作品です。
映画は1985年の発表ですが、上述のとおり日本国内での上映はありませんでした。ただし、今年2025年には、東京ですくない回数であるものの劇場で上映されたようです(チケットはすぐに完売してしまったようですが)。
わたしはブルーレイディスク を注文して見ました。海外映画の円盤といっても、主要な役者はほぼ日本人で(主演は緒形拳 です)、台詞もみな日本語でしゃべっているため、本編視聴においてさほど困るといったことはありません。
2025.tiff-jp.net
タイトルからも察せられるとおり、映画は全4章で構成されています。各チャプターのうち、1~3は三島由紀夫 作品を、4は市ヶ谷駐屯地での出来事を主に描くといった具合で、各章だいたい30分ずつ、ほぼ均等の尺で進行します。
本編冒頭の映像には、黒地に白の文字で、
ー1ー beauty ”Temple of the Golden Pavilion ”
ー2ー art ”Kyoko's House”
ー3ー action ”Runaway Houses”
ー4ー harmony of pen and sword
と、参照したであろう作品が提示されています。
これは上から順に、『金閣寺 』 、『鏡子の家 』 、『奔馬 ―豊饒の海 ・第二巻―』 の英訳タイトルかと思われます。
このほかにも『仮面の告白 』でも語られていた幼少期の出来事や自身をモデルにした写真集『薔薇刑 』の再現カット、ボディビルをはじめて身体を鍛えたこと、映画『憂国 』の撮影現場での一幕、楯の会 結成シーンおよび自衛隊 体験入隊 など、三島由紀夫 自身の人生をなぞった出来事も適宜はさまれていきます。
しかしなんといっても、『Mishima』の持っている映像的魅力は、石岡瑛子 による人工的なまでにつくられた華美でありつつ、しかし海外作品にありがちな東アジア全般をごちゃまぜにした東洋趣味とは異なる印象を与える独特な舞台セット でしょう。
トレーラー映像からも見て取れますが、三島作品をサンプリングしつつ作中作として映像化したシーンでは、意図的にそれが「つくりもの」であることがわかる よう、ライティングを意識した、外部が存在しない屋内撮影の画面ばかりが登場します。
『Mishima: A Life In Four Chapters』ブルーレイディスク 同梱の冊子より。
同冊子より。
ですから、『Mishima』という映像作品においては、三島由紀夫 という人生の各チャプターがそのままある種の舞台(装置)になっている のです。
そもそも『仮面の告白 』からし て、カムアウト、つまりカミングアウト的な小説でありながらも、タイトルに「仮面」という言葉を入れることである種の決定不可能な両義性を与え、ジャンル私小説 における受け手側の反応を意図的にハックするような演技性があったのでした。こうした私小説 の虚構性については、柴田勝二『私小説 のたくらみ: 自己を語る機構と物語の普遍性』 で詳しく論じられています。
また三島由紀夫 は前述の写真集『薔薇刑 』や複数の映画出演以外にも『平凡パンチ 』誌上で読者人気を獲得していたり、1969年にはテレビ局のカメラを入れた状態で、東京大学 で全共闘 の学生らと討論をしていたりするなど、とにかく派手なかたちでのメディア露出やパフォーマンスが多く、加えて自身も多くの戯曲を書いています。
こうした複数の点から三島由紀夫 を自己演出的な人物として(あるいはナルシスティックな人物として)論じる向き
結果的にそうした捉え方は、1970年11月25日の出来事で(三島が事前に大手マスコミであるテレビ局員と新聞記者を市ヶ谷駐屯地に来るよう指示していた経緯もあって)さらに増幅されていったという話は、現代のわたしたちであってもある程度のレベルまでは理路の想像がつくかと思われます。
〈狩りのレヴュー〉における三島由紀夫 表象について
『劇場版 スタァライト 』における〈狩りのレヴュー〉 とは、おおざっぱにいえば、TVシリーズ において人生最高の瞬間である「舞台」の「再演」を望んでいた大場なながその計画に失敗し、しかしその後も期待をかけていた星見純那に対して(主に進路選択において)解釈不一致を起こした結果、「死ね」と自刃を要求する物語 です。
上に引用したインタビューと『Mishima』のトレイラー映像からも確認できるとおり、この〈狩りのレヴュー〉において、金閣寺 が真っ二つに割れる演出アダプテーション されています。同レビュー内で檻がいきなり登場するのも、おそらくは『Mishima』作中での描写からの連想ではないか……と邪推するのは、あながち遠くはない指摘ではないでしょうか。
しかしここにひとつだけ、大きな疑問が残ります。
なぜこのレヴューが「三島由紀夫 」モチーフである必要があったのでしょうか?
まず第一に述べられる理由として、単純に「かっこいいから」というものがあげられます。TVシリーズ のときから大場ななは二刀流の戦闘モンスター的な描かれ方をしており、使用する武器は日本刀です。そこから軍服ふうのデザインモチーフに至るのは、さほど無理のない連想ルートかと思います。
『はいからさんが通る 』にしろ『わたしの幸せな結婚』にしろ、軍服を着た存在は(政治的なモチーフを含みはするものの)大正ロマン 以後のフィクションにおいて、魅力的なかっこいいキャラク ター表象の一類型としてくり返し登場しています。
『わたしの幸せな結婚』第二期 ノンクレジットエンディングより。
しかし今回、あえてその線ではなく、第二の理由を提示し、誤読してみましょう。
つまり、三島由紀夫 も、大場ななも「その後」を生きている人物であり、それは同時に常に「終わり」を意識してきた人物という点で共通している
どういうことでしょうか。
三島由紀夫 は大正14年 (1925年)生まれの人物で、ほぼその人生を昭和日本の歴史(戦前・戦後)と歩みをともにしています。アジア太平洋戦争(第二次世界大戦 )の終結 時には成人しており、彼は勤労動員には応じたものの、最終的に戦地に赴くといったことはありませんでした。
そうして「生きのびてしまった」三島の見た戦後民主主義 を掲げる日本の姿は、天皇 による人間宣言 をはじめ、戦前とはまったく異なるロジックで動いている社会であり、それゆえ戦前から育ってきた彼には欺瞞と矛盾に満ちたものに見えていたのでした。
とはいえ、いま現在、右翼や左翼といった言葉を安易に使ってしまうと、どうしてもこんにちのインターネット上で混線している言説や文脈が自動参照され、この文章を読んでいるみなさんの受け取り方にもぶれが生じてしまう不安があります。
ここではあくまで、三島作品や彼にまつわる言説、そして「三島事件 」での演説における意図と政治的文脈(1970年当時まで)を取り扱い、参照するかたちで「大場なな」というキャラク ターを受け取り、誤読したいと思います。
なぜ「割腹」という表象が選ばれたのか
とはいえ、〈狩りのレヴュー〉のシークエンスを見てすぐに、映像モチーフが『Mishima: A Life In Four Chapters』からのサンプリングであると気づく人はさほど多くはなかったように思われます。そもそも日本で上映していなかったことは、先に古川監督も述べていたとおりです。有名監督のフィルモグラフィー を調べるうちにタイトルに行き着いたとしても、直接見たことのある人はすくなかったことでしょう。
ですから、むしろ『劇場版 スタァライト 』の観客に対してつよく印象づけられたのは「ケリをつける」という言葉の意味があきらかになった瞬間の、星見純那の前に割腹用の刀を寄越したうえ、背後から彼女の首をはねようと刀を構えている大場ななという構図 のほうだと思います。
この構図からわかるとおり、大場なながレヴューに臨んだ目的は「介錯 」です 。割腹、すなわち切腹 してもダメージが入るのは内蔵周辺の部位であり、すぐに絶命することは一般的にむずかしいとされています。よって背後から首を断ち、腹を切った人物が醜態をさらさないよう即死させる(楽にさせる)のが介錯 というおこないです。三島の割腹のさいにも、この介錯 がなされたと言われています。
『Mishima: A Life In Four Chapters』の映像においても、幾度かかたちを変えて三島作品内における「劇的」な「終わり」が強調されていました。特に意識されているのはやはり「死」そのものであり、三島の最期となる市ヶ谷での割腹シーンが ”Runaway Houses”のラストシーンの割腹と重ねるかたちで演出されています。
しかし1970年11月25日の時点では、『豊饒の海 』第二巻『奔馬 』は前年(1969年)に刊行されていたものの、第四巻にあたる『天人五衰 』の原稿はいちばん最後の部分が事件当日になってようやく編集者に手渡された段階であって、書籍として出版されるのは翌年になってからのことでした。
よって、事件が起きたさいの自衛隊 側も、三島読者であった一部の層も、おそらく彼の行動から想起したのはべつの作品と、過去のとある出来事だったと思われます。
では、一連の行動を接続させる文脈とはなんでしょうか。
それは1961年の小説発表から4年後、三島自身の主演によって映画化された『憂国 』 という作品にほかなりません。
『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 』より。
映画『憂国 』(1966年)より。
残念ながらわたし個人は『憂国 』を見る機会にはめぐまれていませんが、台詞がいっさい存在しないこと、ワーグナー がBGMとして流れること、そして全体で30分ほどの映像作品であることなどは知識として持っています。
映画の原作となった小説「憂国 」は2025年現在、新潮文庫 の『花ざかりの森・憂国 』 に収録されているものがいちばん手に取りやすいものかと思います。これは文庫にしておよそ30ページほどの文章量で、ひと息で読み終わることのできる短編です。
eiga.com
ではこの「憂国 」とは、どのような作品だったのでしょうか。物語はいっさいの出来事を、簡潔に冒頭の文章で示すところからはじまっています。
じっさいにその箇所を引用してみましょう。
昭和十一年二月二十八日、(すなわち二・二六事件 突発第三日)、近衛歩兵一聯隊勤務武山信二中尉は、事件発生以来親友が叛乱軍に加入せることに対し懊悩を重ね、皇軍 相撃の事態必至となりたる情勢に痛憤して、四谷区青葉町六の自宅八畳の間に於て、軍刀 を以て割腹自殺を遂げ、麗子夫人も亦夫君に殉じて自刃を遂げたり。中尉の遺書は只一句のみ「皇軍 の万歳を祈る」とあり、夫人の遺書は両親に先立つ不孝を詫び、「軍人の妻として来るべき日が参りました」云々と記せり。烈夫婦の最期、洵に鬼神をして哭かしむの概あり。因みに中尉は享年三十歳、夫人は二十三歳、華燭の典を挙げしより半歳に充ざりき。
「二・二六事件 」は、あえて簡潔な説明で終わらせるのであれば、青年将校 たちによって起こされた軍事クーデターです。彼らは「昭和維新 」を掲げ蹶起しますが、最終的には軍によって鎮圧されます。
「憂国 」の主人公である武山信二中尉は、「二・二六事件 」が起きたさい、何も知らない状態で集合喇叭の音を聞いて軍服を着、軍刀 を佩して自宅から駈け出していきます。家に残された妻の麗子は、ラジオのニュースで事件のことを知り、やがてその内容から良人の親友の名前が蹶起メンバーに含まれていることに気づきます。
武山中尉が帰宅したのは、二十八日の日暮れ時でした。
「俺は知らなかった。あいつ等は俺を誘わなかった。おそらく俺が新婚の身だったのを、いたわったのだろう。加納も、本間も、山口もだ」
武山は、暗黙のうちにこの蹶起メンバーから外されていたのでした。つまり、友人たちと命運をともにすることができなかったことになります。結果的にではあるものの、彼はクーデターを鎮圧する皇軍 側にいる以上、いずれ自分には勅命が下って「叛乱軍の汚名を着た」友人たちを討つことを理解しています。やがて彼はその友情と勅命とのあいだにある自己矛盾を見つめ、妻の麗子に伝えます。
「いいな」と中尉は重なる不眠にも澄んだ雄々しい目をあけて、はじめて妻の目をまともに見た。「俺は今夜腹を切る」
よって、この切腹 の委細を描く物語を戦地に向かうことなく「生きのびてしまった」側 である三島由紀夫 の敗戦体験の再話、ひいてはその延長線上に、国のために死ねなかった自己と戦後の矛盾を解決するための「1970年11月25日」 として見つめることは、さほど乱暴ではない構図かと思います。
また三島由紀夫 は陽明学 における「知行合一 」 を掲げていた人物でもあり、彼が最後に駐屯地でおこなった演説のなかには「自衛隊 が違憲 」であることを集まった自衛官 たちに向かって述べています。
これは戦後民主主義 をはじめ、1960年代から続く安保闘争 の文脈と、日本国憲法 第9条にある「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」という文言に対し、自衛隊 は名目上としては軍にあたらない組織という矛盾、さらには対米関係における従属といったところから発せられる「憲法改正 」であって、2025年現在叫ばれているかたちでの「憲法改正 」のロジックとは方向性がいささか異なる点には注意すべきかと思います。
また以下に挙げる論文も三島由紀夫 の戦後体験、ならびに『憂国 』を理解する補助線として参考になりますので、Ciniiのリンクを貼っておきます。
三島由紀夫の〈敗戦〉 | CiNii Research
三島由紀夫「憂国」論 : 麗子の主体性をめぐるアダプテーション分析 | CiNii Research
さて、この「三島事件 」と「憂国 」とを結びつけることのなにが政治的なイシューたりえたかといえば、映画『憂国 』において割腹する中尉役が三島由紀夫 本人であった うえ、現実に割腹して最期を遂げた彼の演説は「天皇 万歳」という言葉を叫んだことによって締められたという事実です。
よって政治的文脈においては、三島の行動を「二・二六事件 」のような国粋主義 的なクーデターの再演として受け止めない態度が政府や自衛隊 側には求められました。
駐屯地の自衛官 たちは三島に賛同することはありませんでしたが、扇動され加熱していく言説とともに世論が開戦ムードに傾いてしまった戦前日本の愚行をくり返すわけにはいかない以上、自決した三島を国のために殉じた英雄的立ち位置に迎えることは、決して公には許されなかった 、というロジックがはたらくことになります。
加えて、政治的にとくべつな関心はなくとも、世間的にはメディア露出の多い作家が起こした暴力的かつセンセーショナルな出来事であったため、テレビやラジオ、電話を通じて「事件」を知った大衆は、すぐさまその日のうちに書店に殺到し、三島の書籍を買い求めたといいます。この事件以後、映画『憂国 』は遺族の意向もあり、長らく上映ができない状態に置かれました。
「知行合一 」の舞台少女としての大場なな
『憂国 』の内容について触れる以上、どうしても政治的な文脈を経由する必要がありましたが、三島由紀夫 の「美学」という側面から語るのであれば、もうひとつ欠かせない観点があります。それは『Mishima: A Life In Four Chapters』の”Kyoko's House” においても、登場人物の台詞を借りながら語られています。
映像化されているのは『鏡子の家 』において売れない俳優で、ボディビルをはじめた舟木修を中心としたパートです。以下に引用するのは、屋台で舟木修が飲んでいると、日本画 家である山形夏雄がやってきて、すでに同席していた武井ともに芸術談義をするという短いながらもテーマを提示しているシーンです。
ここで意見を交わすのは、武井と山形夏雄のふたりです。位置関係としてはそのあいだに舟木修が座っており、これはそのままキャラク ターの思想的なポジションを反映したように思われます。すこし長いですが、書き起こしてみましょう。
「夏雄ちゃんのほうはどう? 相変わらず絵、描いたの?」
「やってるよ」
「夏雄って山形夏雄さん? あの日本画 の?」
「ええ」
「この前拝見しましたよ」
「そうですか。どうも」
「まあ、人間の身体描かないだけ許せるけど」
「別に悪気ないんだよ。いまちょっと武井さん、彫刻の話してたからさ」
「へえ? どんな話?」
「うん。いやだからね。たとえミケランジェロ でもロダン でも、結局は人間の身体を石かなんかで彫るわけだ。現に生きた人間の身体ってもんがあるってのに。要するに芸術家なんてもんは要らないんだ」
「それじゃ、武井さんが正しいとしましょうか。歯を食いしばって汗を流して、その生きた芸術作品が出来たとしますね。しかしそれが老いさらばえることはどうするんですか? その美しさはどうなるわけ? 作ったあなたが、どうにかしなきゃあならないんだから。だから一番美しいときに死んでしまえばいいんですよ」
また小説『鏡子の家 』については、以下の論文も参考になります。
『鏡子の家』における日常性の問題 | CiNii Research
では『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 』において、大場ななはどのような存在として描かれていたでしょうか。
『劇場版』において、彼女が画面内にはじめて登場するのは、上述した愛城華恋が後輩たちを引き連れていく見学のシークエンスにあたります。
しかし彼女はほかのキャラク ターと違って、後輩から憧れ「見つめられる」存在としては現われません。加えて、画面に大場ななが出てくるひとつ前のカットには、大量の写真(チェキ)と彼女持っている黄色いインスタントカメラ が映っています。ですからむしろ大場ななは「見つめる」側の人 なのです。
ちなみにここに登場するインスタントカメラ は富士フィルム のinstax mini
instax.jp
そしてこのインスタントカメラ がひとつのキーとなっています。
〈狩りのレヴュー〉において、星見純那を組み伏せた大場ななは、そのカメラで彼女をの表情を一枚撮影します。写真とは、その美しい一瞬を閉じ込め、切り取った結果にほかなりません。そのようにして現在を切り取るということは、同時に、未来を見つめようとしないこと でもあります。
ですから、そのような大場ななの口上は、以下のとおりになるのです。
「今は今はと言い訳重ね 生き恥さらした醜い果実
星の遠きに望みを絶たれ 君 死にたもうことなかれ
99期生 大場なな
熟れて落ちゆく定めなら 今 君に 美しい最期を」
ここで述べられている大場ななの口上は「しかしそれが老いさらばえることはどうするんですか?(…)だから一番美しいときに死んでしまえばいい」 という『Mishima: A Life In Four Chapters』で展開された主張に近似しています。だからこそ大場ななの撮影するカメラのレンズには、これから起こるであろう星見純那の自己矛盾や自己欺瞞 といった、言い訳を重ねた醜い未来は映らないのです。
ところで星見純那の提出した「進路希望調査票」は以下のような記載でした。
第一希望 早稲田大学 文学部芸術学部 演劇学科芸術大学 演劇学部
進路面談のシーンにおいて、星見純那は「今はもっと、勉強がしたいんです。舞台のことを客観的に、深く」 と櫻木先生に伝えています。しかしその名目のうちに、演者というルートに向かわなくてよい理由を、つまり「言い訳」を、「生き恥」をさらしているのだと大場ななは暗に糾弾しているのです。であれば、いまはまだ輝かしい未来のある演者であるうちに死んでくれたほうがずっとよい、というわけでしょう。
こうして自身の思想と行動を一致させようとする(純那ちゃんの解釈違いを許さない点において)大場ななは 「知行合一 」を実践する舞台少女である といえるはずです。
舞台(演者であること)から暗に降りようとする星見純那に自刃を要求した大場ななは、「二・二六事件 」のメンバーから暗に外された武山中尉の自己矛盾を解決する(友を殺さず、そして国のためを思う)手段と目的の一致としての「割腹」、すなわち戦場で散ることなく生きのびた三島由紀夫 という作者から登場人物に向けてなされた「美」のための要求と、相似形の構図のなかにあるのです。
劇場版のテーマとして改めて提示される「怖れ」
本作、というよりも『スタァライト 』のアニメシリーズ全編にわたって、常にメタ的な視点を持ち、自覚的な振る舞いをしていたのが大場ななという舞台少女でした。
それゆえに劇場総集編『少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド』はストーリーテラー 的な立ち位置を務めます し、『劇場版』においても、ほかの少女たちをふたたび舞台の上に引きずり出したのも彼女でした。ですが同時に、大場なな自身もまたひとりの苦悩する舞台少女であったこと を忘れてはいけないと思います。
上述したとおり、『劇場版』における大場ななの初登場は、進路面談のシーンです。そこで提出された「進路調査希望票」には以下のように記されていました。
第一希望 新国立第一歌劇団 俳優部歌劇団 制作部
大場ななと担任の櫻木先生は、これを参照しつつ会話をつづけます。
「出席番号15番、大場ななです」
(櫻木先生、調査票を確認して)
「舞台に立つべきか、舞台をつくるべきか」音楽学 院に来て、はじめて知ったんです。みんなで舞台に立つ眩しさ。みんなで舞台をつくる喜びを。わかっているんです。決めなくちゃいけない。いつかは終わるんだって。でも、舞台に立つことも、つくることも、どちらも大切で……大好きだから」
じつのところ『劇場版』において、彼女が明確に自分の進路に対する逡巡を伝えてみせるのは、ほぼこのシーンくらいしかありません。
ですから「みんな喋りすぎだよね」 と一歩引いて口にする大場ななの台詞は、じつは自身への皮肉もふくまれていることになります。なぜなら彼女は、おなじ99期生に甘えることさえできず、自分自身もまた「知行合一 」的な舞台少女そのものにはなれず、一貫性のある結論が出ない悩みを抱えており、しかし最終的にはその物語を星見純那へと仮託しようとしていた わけですから。
そしてもうひとつ、『劇場版』においてはじめて登場し、くり返し用いられる象徴的なフレーズとして「列車は必ず次の駅へ。では舞台は? 私たちは?」 というものがありましたが、じつのところ、この歯切れのよい実存的問いかけを内包する言葉には、もっとシンプルで根源的な感情が覆い隠されています。
『劇場版』でのレヴューを通じて舞台少女たちはみな、自身の感情と向き合い次の舞台へと進む決意をするわけですが、しかしじつのところ、それよりもずっと前に、ほかのキャラク ターがおなじ感情を叫んでいた事実を、みなさんにも思い出していただきたいと思います。
「あ~~~~~怖いなぁ~~~~!
第100回、あの『スタァライト 』を超えられるのか、ほんとに怖い!
でも、怖くて当たり前だよね。私たち卒業公演なんてはじめてだし、先輩たちだってみんな怖かったと思うんだ。でも、みんなとなら。私たち99期生だけでつくる、最後の舞台だもん。立ち止まっていられない! 最後までつくりたい! みんなと!」
そう、99期生の「スタァライト 」決起集会のシーンです。本作においてくり返し舞台少女たちが問われるのは、じつのところ「怖い」という感情のさまざまな側面です。
関係が変化することへの怖れ、約束を信じつづける怖れ、分かれ道への怖れ。なにより、過去を乗り越えられるかどうかわからない、という怖れ。
もちろんこの、過去を乗り越える 、というテーマはTVシリーズ でもくり返し語られた部分にほかならないのですが(たとえば「舞台少女は日々進化中」「アタシ再生産」といったフレーズなど) キャラク ターが「高校3年生」という立場になったことにより、この問いは改めて「進路」という眼前のテーマとして再生産されているのです。
にもかかわらず、わたしたち観客は、TVシリーズ で戦った舞台少女たちへの愛着があったがために(直前に大場ななに皆殺しされたショックから抜けきれないこともあり)、この決起集会で舞台創造科のキャラク ターが放った言葉や脚本が実質的なテーマ宣言であったことに 、まだ気づけません。 そしてそれは、これからそれぞれのレヴューに立つことになる舞台少女たちもまた、おなじなのです。
ふたたび、「割腹」という表象について
〈狩りのレヴュー〉の後半部における核心は、「君は、眩しかったよ」と大場ななが見捨てるように過去形にした、かつてまなざされる対象であった星見純那が立ち上がって反撃し、その用意された舞台を文字通り切り開き、乗り越えてみせる点にあります。
星見純那が口上を述べたのち、レヴューは切腹 のための刀を置く台≒三方(さんぽう)を模した舞台上での戦いとなり、画面はTVシリーズ 7話を思わせる黄色い光に染まります。もちろんこれは大場ななの求めていた人生最高の瞬間を取り戻そうとする、「再演」のための色を想起させるものですが、このレヴューではどこか薄いもやが漂っているかように、画面の見通しはすこしだけ悪くなっています。
剣戟のなかでトレードマークの眼鏡さえ弾き飛ばし、「目の前すら見えなくなった君に、もう星を掴むことなんて、できない」 と大場ななは相手に向かって告げます。しかし星見純那は泥臭く立ち上がり、あがくことをやめません。そこではじめて大場ななは、その彼女の姿に動揺を隠せなくなります。
「私の純那ちゃんは、そんなやつじゃない! 私の純那ちゃんじゃ……ない……お前は何者だ……お前は何者だ! 星見純那ッ!」
「貴女に与えられた役なんか、要らない。私の道は、私が、切り開く! 貴女が用意した舞台なんて、全部、全部切り捨てる!」
その言葉にあわせてもう一度、舞台となっていた三方が真っ二つに切断される演出 が入ります。そう、だいぶ前に引用したインタビューのなかで、古川監督自身が語っていた、あの『金閣寺 』パートでの演出にほかなりません。
この映画でも金閣寺 の描写があります。少年が金閣寺 の美しさに魅了されるんですが、そこで金閣寺 が真っ二つに割れちゃう んですよ!
『Mishima: A Life In Four Chapters』トレイラーより。
そして、この舞台の切断とともに、星見純那は最後の啖呵を切ってみせます。
「目が眩んでるのは貴女のほうよ! だってこの舞台の私は……この舞台の私が! 眩しい主役、星見純那だ!」
〈狩りのレヴュー〉より。文字通り舞台を切り開き、かつての想像を飛び越える。
〈狩りのレヴュー〉より。「今」の星見純那に集まる光を、大場ななは目撃する。
こうしてレヴューは終わり、舞台は崩れ、壊れ、落ち残ったのは、かつて光を放っていたはずの、再演を照らそうとする大場ななの思想を象徴していたはずの、塔の残骸とふたりだけです。ですから〈狩りのレヴュー〉で星見純那は腹を切ることもなければ、大場ななによってその首を斬り落とされることもありませんでした。
では、この舞台はいったいなんだったのでしょうか。おそらくですが、ここで殺されるに至ったのは、〈大場ななの用意した舞台〉という「再演」の概念そのもの です。
つまり、大場ななが固執 していた「過去」の姿を、星見純那が「今」の輝きによって乗り越え、魅了することで、その「執着」を介錯 してやった ということです。
「劇的」な「終わり」≒「割腹」のモチーフは塔の切断によって完成する。
三島由紀夫 作品において、くり返し語られてきた「美」と「終わり」の姿。自己矛盾を行動によって一致させる方法としての「割腹」。改めて述べますが『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 』において、大場ななの思想は「再演」という「過去」≒「最高の瞬間」を再び求めるも失敗し、「その後」を「生きのびてしまった側」としての視点から生まれてきた思想でした。
だからこそ、彼女にとっては、醜くなってしまう未来を殺すということが「ケリをつける」という意味であり、しかしその象徴としての塔を「切腹 」させることでレヴューは幕を下ろします。
かつてあった輝かしい頂きに目が眩み、ずっと「過去」を求めてしまうこと。その不可能性あるいは自己矛盾を終わらようと言ったのに対し、純那ちゃんは「未来」に恐怖を抱いたとしても、見つめてくれる相手の懐に飛び込んでみせる「今」を示した のです。大場ななに「過去」ではなく、「今」の自分を見ろ、と。かつてあれほどまでに過去の偉人や文学者の言葉を引用し、それが「私の力だ」と述べていた星見純那が、いまだ存在していない世界の側にはじめて手を伸ばしたのです。
だとするなら、「過去」に執着していたのは、星見純那もおなじだった 、とも指摘することはできないしょうか。文学とは「書かれたもの」であり、「過去」だからです。そしてその「過去」を代表するラスボスであるかのように大場ななが三島由紀夫 モチーフをまとって登場し、「終わり」を宣告する舞台をつくった。ですからそれは星見純那にとって、いつかは立ち向かうべき必然であり、潜在的 な「怖れ」の対象だったのだと思います。
こうした「怖れ」への対峙は『劇場版』において、何度もかたちを変えて検討されていくことについては、本映画を見た方であれば、きっと同意できるでしょう。
大場なながほんとうに「怖れていたもの」とはなんだったのか
ほんとうなら、ここでもう記事を終えてよいタイミングなのですが、あえてト書きにはならないような、さらなる誤読を進めたいと思います。
先ほど、わたしは『劇場版』のテーマが「怖れ」であるということ、またそれに対峙し、乗り越えていくことこそがかたちを変えて反復されている点を述べました。では、大場ななにとっての「怖れ」とはなんだったのでしょうか。 星見純那が解釈違いの、愚かしく眩しい存在ではなくなっていくこと、主役を求めることさえ諦める姿、だったのでしょうか。
わたしは、そうは受け取りません。
なぜなら、〈狩りのレヴュー〉のあと、大場ななは、星見純那からのとある言葉を受け、次の舞台に向かおうとしながらも、涙を流してしまうからです。
「でも、いつか。いつか、また。新しい舞台で。一緒に」
「またね。星見純那」
「またね。大場なな」
もしかすると、大場ななは、星見純那が舞台の世界に二度と戻らない可能性を怖れていたのではないでしょうか。
『劇場版』の進路面談シーンで提出した「進路希望調査票」からも確認できるとおり、星見純那の第一志望は「早稲田大学 文学部」です。2025年現在、ネットの情報からもうすこし細かく調べてみると、早稲田大学 において舞台を学べるところは、正確には「早稲田大学 文学部 文学科 演劇映像コース」 であるといえそうです。おそらく彼女も念頭に置いていたのは、このコースではないでしょうか。
www.waseda.jp
では、なぜ星見純那が希望するような「演劇を学ぶための進路」に対して、大場ななは「割腹」を求める行動に出たのでしょうか 。いったい、なにが彼女を怖れさせていたのでしょうか。ですからわたしはここに、「1970年11月25日」からのエコー をもう一度、聴き取ってみたいと思います。
一九七〇年十一月二十五日のあの奇妙な午後を、僕は今でもはっきりと覚えている。強い雨 に叩き落とされた銀杏の葉が、雑木林にはさまれた小径を干上がった川のように黄色く染めていた。僕と彼女はコートのポケットに両手をつっこんだまま、そんな道をぐるぐると歩きまわった。落ち葉を踏む二人の靴音と鋭い鳥の声の他には何もなかった。
(…)
我々は林を抜けてICUのキャンパスまで歩き、いつものようにラウンジに座ってホットドッグをかじった。午後の二時で、ラウンジのテレビには三島由紀夫 の姿が何度も何度も繰り返し映し出されていた。ヴォリュームが故障していたせいで、音声は殆んど聞きとれなかったが、どちらにしてもそれは我々にとってはどうでもいいことだった。我々はホットドッグを食べてしまうと、もう一杯ずつコーヒーを飲んだ。一人の学生が椅子に載ってヴォリュームのつまみをしばらくいじくっていたが、あきらめて椅子から下りるとどこかに消えた。
「君が欲しいな」と僕は言った。
「いいわよ」と彼女は言って微笑んだ。
我々はコートのポケットに手をつっこんだままアパートまでゆっくりと歩いた。
上に長く引用したのは、1968年、早稲田大学 第一文学部に入学、演劇専修 *2 へ進み 、三島由紀夫 の自決の日と同時代に学生生活を過ごし、最終的には作家となった人物による小説です。
このような光景がじっさいに国際基督教大学 の構内に存在していたかどうかは、記録が残っていない以上、判断のむずかしいところですが、この作家が、学生闘争の時代における暴力的な手段や内ゲバ といったものに対して、多くの作中で距離を置いた記述をしてきたことはある程度まで指摘できます。
三島由紀夫 の起こした行動や、呼びかけに対して、そもそも音さえ届かなかった状況から物語がはじまっている点は、そのうえで考えると象徴的です。
つまり、なにが言いたいかといえば。
大場ななは、「星見純那が小説家になる未来」を怖れたのではないでしょうか 。
その場合、かつて舞台少女だったふたりの道は、すくなくとも舞台の上の俳優としては交わらない可能性のほうが、ずっと高くなることは想像にかたくありません。だからこそ、大場ななは「新しい舞台で。一緒に」 と約束となりうる言葉を告げられて、「今」の先にある「未来」を見つめられるようになったのではないしょうか。
そうです。
先に引用した文章は、村上春樹 『羊をめぐる冒険 』「第一章 1970/11/25」
だからこそ、大場ななの「怖れ」というのはその「未来」から生まれていた のだと、自分は考えます。大好きな人と、決して交わらない未来というものを、彼女はなによりも怖れていたのではないでしょうか。
ところで『羊をめぐる冒険 』では、先ほど引用した文章のあと、一行の空白があり、時間が飛びます。次のシーンは午前二時の真夜中から書かれています。
僕がふと目覚めた時、彼女は声を出さずに泣いていた。
そして〈狩りのレヴュー〉で印象的にくり返されるのは、涙にまつわる台詞でした。
「泣いちゃった」
ーーーー終幕(カーテン・フォール)。
その他、直接言及しなかった参考文献ほか
cir.nii.ac.jp www.waseda.jp
エンディング:Widescreen Baroque「Door to Door」
VIDEO www.youtube.com
ちょっとした告知
virtualgorillaplus.com
映画『この本を盗む者は』 の劇場公開に先駆けて、深緑野分による原作小説の魅力を紹介する記事を、VGプラスさまで書かせていただきました(織戸久貴名義)。
X(旧Twitter )およびBlueskyと連動した特製図書カードプレゼント企画(2025/12/2締め切りです!)もあります ので、ふるってご応募ください。
12/26公開の劇場アニメーション 『 #この本を盗む者は 』に備えて📘 織戸久貴 @nanamenon.bsky.social さんが、深緑野分さんの原作小説の魅力を紹介✨ 読書が生む“イマーシブ”な体験、その根源にあるものは virtualgorillaplus.com/nobel/whoeve... さらに! 🎁特製図書カードを5名様にプレゼント ✅応募 ① @vagopla をフォロー ② この投稿をRT ⏳締切:12/2(火) 詳細は記事の最後に👀
— SFメディア バゴプラ (@vagopla.bsky.social) 2025-11-26T03:02:20.801Z
bsky.app
ぜったい見てくれよな!


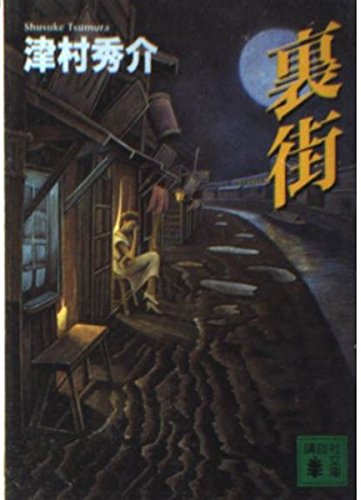
















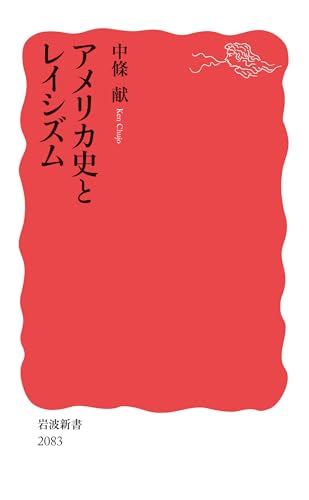






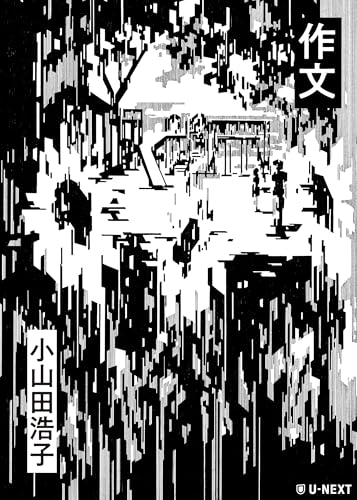
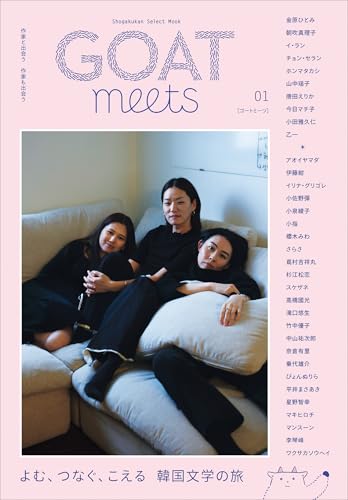


![文學界 2025年10月号[雑誌] 文學界 2025年10月号[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51nAZmMRGQL._SL500_.jpg)












![Criterion Collection: Mishima: Life in Four / [Blu-ray] Criterion Collection: Mishima: Life in Four / [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/5186+zBqsXL._SL500_.jpg)



![三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実 [Blu-ray] 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51c7ISJeLvL._SL500_.jpg)

















